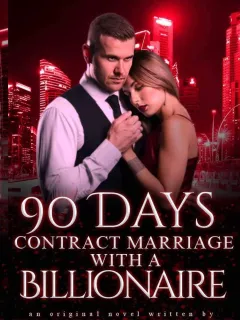90 Days to Seduce the Mafia Boss
Ongoing · Luna Scribe
"You're trembling," he said softly.
I was unable to talk. Then, slowly I felt his fingers move up my thigh. They moved under my dress, brushing past the soft skin. I shivered. His fingers slid higher, between my legs.
I inhaled sharply. Without asking, he located my panties and pushed them away. He ran his fingers along my slit, slow at first. I bit my lip, trying to stay still. He circled my clit once, twice, then dipped lower. A finger slid inside me without warning.
"You saw what you are not supposed to see baby doll, but I will pretend you are smart enough to know better."
He added another finger, stretching me.
"Look at me," he said.
I lifted my eyes.
"I want to see your face while I ruin you."
His fingers moved faster, curling inside me, hitting that place again and again. My moans spilled out now, uncontrolled. I forgot the mission. I forgot everything but his hand between my thighs.
And did I mention, Luis is still in the room!
He leaned in, his mouth close to my ear.
"You're nothing but a toy," he whispered. "And toys don't get to feel this good unless I allow it."
I was scared, but my hips moved with him. I hated him. I feared him. But I couldn't stop the way I moved against him...
Zita Antonio is in deep trouble. Her gambling father has bitten off more than he can chew, and her mother is slowly dying by the day.
On her way back from her shitty job at a café downtown, she's kidnapped by unknown men and brought to their boss. They blindfold her so she cannot see.
This mysterious man is one of her father's many creditors but he might just be the most dangerous.
He gives her three options:
Pay back the millions her father owes, die with her family or become his pawn.
Of course she chooses the option that seems simple. Pawn.
However, this might just be the most dangerous of them all.
This mysterious man wanted her to retrieve a valuable document from the mansion of Dario Giovanni- the most powerful man in all of Europe.
And to do it? Well she first had to seduce her way in…
I was unable to talk. Then, slowly I felt his fingers move up my thigh. They moved under my dress, brushing past the soft skin. I shivered. His fingers slid higher, between my legs.
I inhaled sharply. Without asking, he located my panties and pushed them away. He ran his fingers along my slit, slow at first. I bit my lip, trying to stay still. He circled my clit once, twice, then dipped lower. A finger slid inside me without warning.
"You saw what you are not supposed to see baby doll, but I will pretend you are smart enough to know better."
He added another finger, stretching me.
"Look at me," he said.
I lifted my eyes.
"I want to see your face while I ruin you."
His fingers moved faster, curling inside me, hitting that place again and again. My moans spilled out now, uncontrolled. I forgot the mission. I forgot everything but his hand between my thighs.
And did I mention, Luis is still in the room!
He leaned in, his mouth close to my ear.
"You're nothing but a toy," he whispered. "And toys don't get to feel this good unless I allow it."
I was scared, but my hips moved with him. I hated him. I feared him. But I couldn't stop the way I moved against him...
Zita Antonio is in deep trouble. Her gambling father has bitten off more than he can chew, and her mother is slowly dying by the day.
On her way back from her shitty job at a café downtown, she's kidnapped by unknown men and brought to their boss. They blindfold her so she cannot see.
This mysterious man is one of her father's many creditors but he might just be the most dangerous.
He gives her three options:
Pay back the millions her father owes, die with her family or become his pawn.
Of course she chooses the option that seems simple. Pawn.
However, this might just be the most dangerous of them all.
This mysterious man wanted her to retrieve a valuable document from the mansion of Dario Giovanni- the most powerful man in all of Europe.
And to do it? Well she first had to seduce her way in…