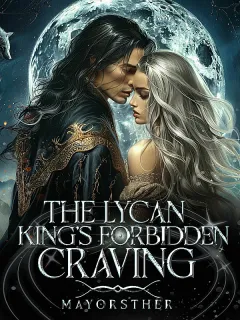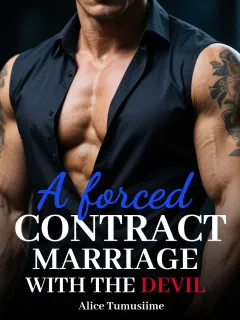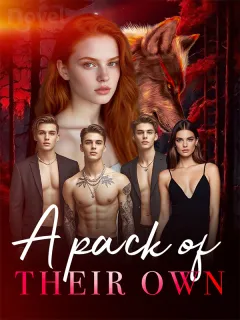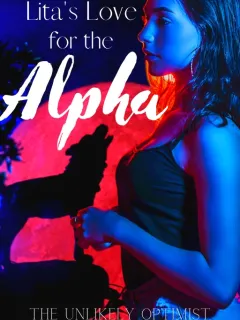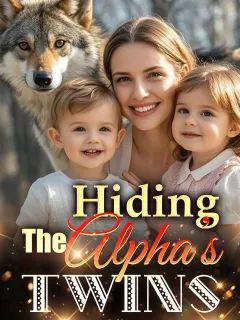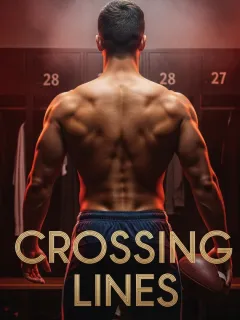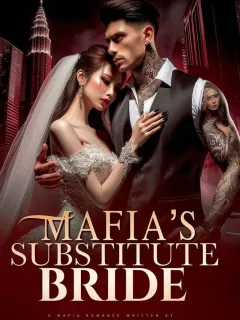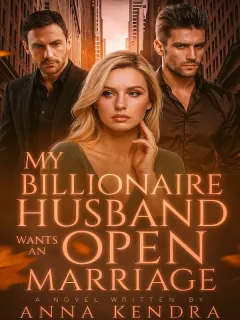The Lycan king's Forbidden Craving
Ongoing · Esther Olabamidele
"End her, and burn her body."
Those words rolled off cruelly from the tongue of my destined one-MY MATE.
He stole my innocence, rejected me, stabbed me, and ordered me to be killed on our wedding night. I lost my wolf, left in a cruel realm to bear the pain alone...
But my life took a twist that night-a twist that dragged me into the worst hell possible.
One moment, I was the heir to my pack,...
Those words rolled off cruelly from the tongue of my destined one-MY MATE.
He stole my innocence, rejected me, stabbed me, and ordered me to be killed on our wedding night. I lost my wolf, left in a cruel realm to bear the pain alone...
But my life took a twist that night-a twist that dragged me into the worst hell possible.
One moment, I was the heir to my pack,...
162k Views