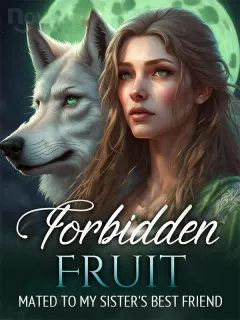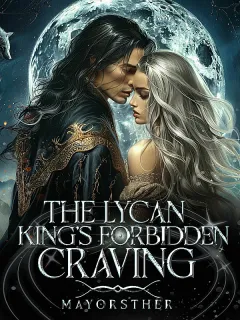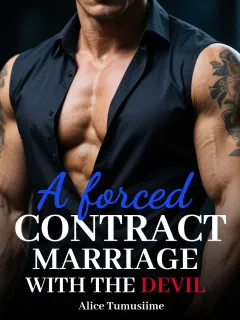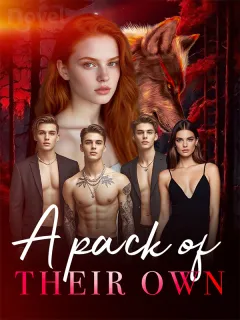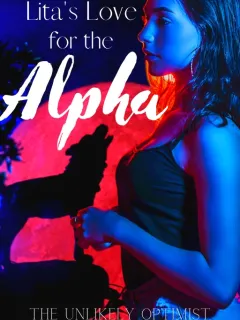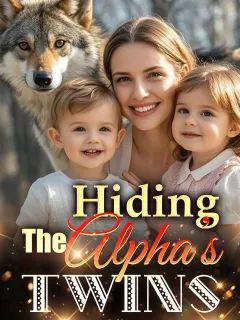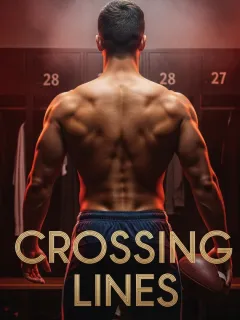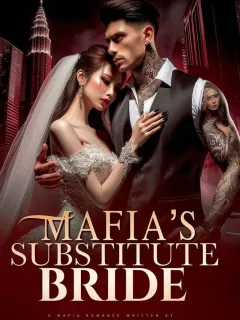HIS DOE, HIS DAMNATION(An Erotic Billionaire Romance)
Ongoing · Vivien Jumbo
Trigger/Content Warning:
This story contains mature themes and explicit content intended for adult audiences(18+). Reader discretion is advised.
It includes elements such as BDSM dynamics, explicit sexual content, toxic family relationships, occasional violence and strong language.
This is not a fluffy romance. It is intense, raw and messy, and explores the darker side of desire.
“Take off ...
This story contains mature themes and explicit content intended for adult audiences(18+). Reader discretion is advised.
It includes elements such as BDSM dynamics, explicit sexual content, toxic family relationships, occasional violence and strong language.
This is not a fluffy romance. It is intense, raw and messy, and explores the darker side of desire.
“Take off ...
609.3k Views